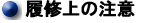| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 平野 眞由 講師 | 4 | 1~4 | 通年 | 土 | 1 |


| 第1クール(第1~7回)では、昨年度話題となったドラマ『半沢直樹』の舞台となった銀行が扱っている法のうち、民法、会社法、手形法・小切手法、民事訴訟法等及びこれらの関連法の一部について学ぶ。法専門科目の紹介という意義も有する。 第2クール(第8回以降)では、民法の契約以外(相続・離婚・事故等)の概要について、学習する予定である。 |
| なお、第2クール以降(第8回以降)は、受講者の意見・要望等を聞き再度内容吟味をしたうえで、授業計画を変更する可能性もある。 |