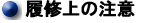| 1 |
演技論とは何か/リアルな身体とは何か/人類学と演技論 |
| 2 |
西洋(フランス)演劇史概観/近代劇における音楽の排除と演技論 |
| 3 |
工業化と音楽的身体の排除 一七〜一九世紀 |
| 4 |
弁論術教育と近代優美演技論(クライスト「人形芝居について」) 一六〜一八世紀 |
| 5 |
なぜ古代演技論か/古代演技論とは何か |
| 6 |
演劇の誕生と演技論の生成 前六世紀〜前五世紀 |
| 7 |
プラトン演技論(1) 「神がかり」の理論とピンダロス的生得主義 |
| 8 |
プラトン演技論(2) イソクラテス弁論術への批判と音楽論的悲劇論 |
| 9 |
アリストテレスの演技論(1) 反プラトン的演劇論 |
| 10 |
アリストテレスの演技論(2) 弁論術批判としての演技論、デモステネス批判 |
| 11 |
アリストテレスの演技論(3) 新たな語りの形態学を求めて |
| 12 |
ヘレニズム演劇における悲劇の再音楽化 |
| 13 |
発表(1) |
| 14 |
一学期まとめ |
| 15 |
予備日 |
| 16 |
キュニコス派(犬儒派)の人生論的演技論 |
| 17 |
初期ストア派の演技論 ストア派におけるキュニコス派演技論の継承と「訓練」の概念 |
| 18 |
中期ストア派の演技論(1) ディオゲネスのプラトン的演技論 |
| 19 |
中期ストア派の演技論(2) 中間的音楽性の演技論 デュボス『詩画論』とロンギノス『弁論術』 |
| 20 |
中期ストア派の演技論(3) パナイティオスの優美演技論と中期ストア派のアリストテレス的展開 |
| 21 |
ヘレニズム演技論の美学的展開 アリストテレスの「仕事の美学」と悲劇の快 |
| 22 |
感情主義的演技論の成立と言語論 ホラティウスとエピクロス派/ストア派言語生成論 |
| 23 |
ローマ弁論術における演技論(1) ローマ演劇とは何か 俳優と弁論家 |
| 24 |
ローマ弁論術における演技論(2) ローマ弁論術における優美概念と俳優の社会的地位 |
| 25 |
ローマ弁論術における演技論(3) 「気取り」の概念 |
| 26 |
ローマ弁論術における演技論(4) 嘆き歌と「アジア的」弁論術、「朗誦法」の起源 |
| 27 |
古代演劇における「アジア的」なものと音楽性の排除 |
| 28 |
発表(2) |
| 29 |
二学期まとめ |
| 30 |
予備日 |