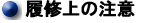| 1 |
イントロダクション -今、“関税”・“税関”に起きていること-(財務省関税局総務課長 柴﨑澄哉) |
| 2 |
関税とは何か? “7,433”-それぞれの関税率に込められた意味-(財務省関税局関税課関税企画調整室長 西野健) |
| 3 |
関税をめぐる国際的な動向(1) 世界経済のブロック化を脱却せよ -多角的自由貿易体制の確立-(財務省関税局局付(青山学院大学経営学研究科特任教授、前財務省関税局関税課世界貿易機関専門官) 近藤嘉智) |
| 4 |
関税をめぐる国際的な動向(2) 国際通商の憲法 -WTO(世界貿易機関)協定-(財務省関税局局付(青山学院大学経営学研究科特任教授、前財務省関税局関税課世界貿易機関専門官) 近藤嘉智) |
| 5 |
貿易救済措置 -セーフガードやアンチダンピングなど、グローバル化の安全弁-(財務省関税局関税課関税企画調整室長 西野健) |
| 6 |
関税をめぐる国際的な動向(3) 多角的自由貿易体制の限界と地域主義の拡大 -国際通商の特別法としてのFTA(自由貿易協定)、EPA(経済連携協定)-(財務省関税局関税課(参事官室)課長補佐 中尾崇) |
| 7 |
税関行政(1) 輸入品は必ず“ここ”を通ってくる -グローバルサプライチェーンの関所-(財務省関税局業務課課長補佐 中西佳子) |
| 8 |
税関行政(2) EPA関税率の適用を左右する原産地のルール -フランス産のぶどうを原料としてスイスで醸造・瓶詰めしたワインに日スイスEPAのEPA税率は適用できる?EPAにおける原産地のルールの交渉はどのように行っている?-(財務省関税局関税課兼業務課課長補佐 香川里子) |
| 9 |
税関行政(3) 何をもとに関税額を決定するか -貨物の価格だけ?運賃は?ロイヤルティは?そのルールは日本が勝手に決めているの?-(財務省関税局関税課課長補佐(前財務省関税局業務課課長補佐) 正海伸幸) |
| 10 |
税関行政(4) 覚せい剤・拳銃・コピー商品等の密輸を最前線で食い止める(財務省関税局関税課国際協力専門官(前財務省関税局監視課課長補佐) 鈴木崇文) |
| 11 |
税関行政(5) 国際物流のセキュリティ強化と貿易円滑化の両立 -今求められる官民パートナーシップ-(財務省大臣官房専門調査官兼関税局管理課(元財務省関税局業務課認定事業者調整官) 米山徹明) |
| 12 |
税関行政(6) 法執行のダイナミズムを体感する -税関見学を通じて- |
| 13 |
多様化する税関業務と各国税関の調和 -我が国税関の“知”をグローバル・スタンダードにするために-(財務省関税局参事官(国際協力担当) 田中秀治) |
| 14 |
政策提言 税関行政の今後について(財務省関税局総務課長 柴﨑澄哉) |
| 15 |
総括 |