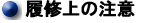●
社会調査法Ⅱ
| 担 当 者 |
単 位 数 |
配当年次 |
学 期 |
曜 日 |
時 限 |
|
大山 昌彦 講師
|
2 |
2~4 |
第2学期 |
火 |
5 |

-
私たちのまわりにはたくさんの「調査」が存在しています。そしてその成果は私たちの社会生活に少なからぬ影響を与えています。しかし、私たちが目にするほとんどは最終的な結果に限定されています。そのため調査がどのように行われ、どのようにデータがとられ、どう分析されるのかといった内実を目にすることはほぼ皆無でしょう。この講義の目的は、社会を調査する方法を、実際にその体験することから学ぶことを目的としています。この講義では質問票調査を中心とした量的な調査方法を中心に扱っていきます。受講者は「社会調査法Ⅰ」をあわせて履修することを強く推奨します。

-
| 1 |
イントロダクション |
| 2 |
グループ分けと問題意識の設定 |
| 3 |
問題意識と仮説の設定 |
| 4 |
調査票の作成(1)仮説をふまえた質問項目の作成 |
| 5 |
調査票の作成(2)質問文の作成 |
| 6 |
調査票の作成(3)プリテストを通じた調査票の修正 |
| 7 |
調査の実施と注意 |
| 8 |
データの入力とクリーニング |
| 9 |
データの分析(1)度数分布表の作成と結果の解釈 |
| 10 |
データの分析(2)度数分布表の作成と結果の解釈 |
| 11 |
データの分析(3)クロス集計表の作成と解釈 |
| 12 |
図表の作成とレポートに関する注意 |
| 13 |
レポートの作成案の発表 |
| 14 |
授業のまとめ |
| 15 |
予備日 |

-
講義および受講生の課題のフィードバックを中心にすすめます。

- レポート:60%(論理的な内容になっているか。適切な分析と解釈が行われているか。)
- 課題の内容:40%(講義の内容を理解し指示通りに課題をこなしているか。)

-
森岡清志『社会調査ハンドブック』第2版、日本評論社、2007年、ISBN=4535582467
-
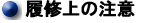
-
履修者数制限あり。(30名)
第1回目の授業に必ず出席のこと。

-
初回の講義で全体の授業内容について解説するので、必ず出席して下さい。
本講義は演習の要素もあるため、ほぼ毎回出席しないと、単位取得は難しいと考えてください。
グループ作業を行うため、個々人が責任を持って授業に参加して下さい。途中で放棄すれば他のメンバーの迷惑になります。