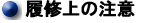| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 和光 純 教授 | 2 | 1~4 | 第2学期 | 木 | 1 |


| 1 | 簡単な分数関数と指数関数の積分、確率変数の期待値 |
| 2 | ベクトルの和・差・スカラー倍・内積 |
| 3 | 行列の定義、行列の和・差・スカラー倍 |
| 4 | 行列の積 |
| 5 | 連立方程式と逆行列、行列式 |
| 6 | ベクトルの1次独立性と行列のランク |
| 7 | 中間テスト |
| 8 | 偏微分の方法と偏微分係数の意味 |
| 9 | 2階偏微分係数の経済学的意味 |
| 10 | 合成関数の偏微分 |
| 11 | 2変数関数の極大・極小 |
| 12 | 全微分、接平面、無差別曲線の接線 |
| 13 | 条件付極大化問題とラグランジュ乗数法:最適消費計画を立てる |
| 14 | ラグランジュ乗数の意味 |
| 15 | 短期費用関数と長期費用関数の関係:包絡線定理 |