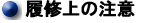| 1 |
授業の方針、年間授業計画、受講上の注意、イントロダクション:「哲学史」とは何か |
| 2 |
キルケゴール(1):普遍的真理に対する反抗。「理性」から「実存」へ-実存主義の先駆者としてのキルケゴール |
| 3 |
キルケゴール(2):『死に至る病』(1849)における「絶望」の現象学 |
| 4 |
ニーチェ(1):ショーペンハウアーからニーチェへ。「生」の哲学の立場。「真理への意志」の虚構性。「生への意志」から「力への意志」へ |
| 5 |
ニーチェ(2):芸術論-『悲劇の誕生』(1872)を手引きに |
| 6 |
ニーチェ(3):道徳批判・キリスト教批判-『善悪の彼岸』(1886)と『道徳の系譜』(1887) |
| 7 |
ニーチェ(4):「超人」・「永劫回帰」・「力への意志」-『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883‐85) |
| 8 |
実証主義:positivismとは何か。A・コント、E・マッハ |
| 9 |
功利主義:ベンサム、J-S・ミルなどの19世紀イギリス倫理学 |
| 10 |
ディルタイ(1):「歴史的生の構造連関」・「体験」・「表出」・「理解」 |
| 11 |
ディルタイ(2):「解釈学」とは何か。「精神科学における歴史的世界の構成」(1910) |
| 12 |
ベルクソン(1):「直観」と「持続」。フランス・スピリチュアリスムの伝統。 |
| 13 |
ベルクソン(2):ゼノンの「パラドックス」、カントの「時間」概念などをめぐって |
| 14 |
新カント派(マールブルク学派、西南ドイツ学派):自然科学と価値問題への寄与としての哲学 |
| 15 |
第一学期の復習および第二学期への展望 |
| 16 |
フッサール(1):『論理学研究』(1900)、「現象学」とは何か、「還元」・「エポケー」・「本質直観」 |
| 17 |
フッサール(2):「他者」、「感情移入」、「生活世界」 |
| 18 |
フッサール(3):フッサールの「像意識」理論。カンディンスキーの抽象絵画論 |
| 19 |
フッサールからハイデッガーへ:「超越論的意識」の存在とは何か。「主観」Subjektから「現存在」Daseinへ。 |
| 20 |
ハイデッガー(1):『存在と時間』(1927)-「存在の意味への問い」、「世界の世界性」、「現存在の日常性」、「死への存在」、「時間性」、「歴史性」 |
| 21 |
ハイデッガー(2):後期ハイデッガーの根本問題-『哲学への寄与論稿』(1936-38)、ヘルダーリン論、ニーチェ講義、「理由律」-「技術」-「立て組み」批判 |
| 22 |
ハイデッガー(3):『芸術作品の根源』(1936)(「物」・「道具」・「作品」)、クレーとセザンヌの絵画の解釈 |
| 23 |
ハイデッガー(4):東アジア的思惟との対話の可能性(芭蕉の俳句とハイデッガー) |
| 24 |
ヤスパース:実存哲学と歴史哲学-「包括者」、「実存開明」、「暗号」、「枢軸時代」、「大衆」 |
| 25 |
メルロ=ポンティ(1):身体の現象学-「肉」・「幻影肢」・「交差配列」(キアスム) |
| 26 |
メルロ=ポンティ(2):絵画論・セザンヌ論-『眼と精神』(1964) |
| 27 |
ウィリアム・ジェイムズ:「純粋経験」、「プラグマティズム」 |
| 28 |
日本における現象学(フッサール、ハイデッガー)の受容と展開(西田幾多郎、和辻哲郎、三宅剛一) |
| 29 |
質疑応答 |
| 30 |
一年間のまとめ。そして次年度に講じる第四部への展望 |