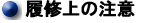| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 本間 紀子 講師 | 4 | 1~2 | 通年 | 月 | 2 |


| 1 | イントロダクション |
| 2 | 美術の起源と美術制作の動機(1,2)※以下、( )内は『美術の物語』の章の番号です。 |
| 3 | ギリシャ美術(3) |
| 4 | ギリシャ美術とその広がり(4) |
| 5 | ローマ美術と初期キリスト教美術(5) |
| 6 | ビザンティン美術(6)、東方の美術(7) |
| 7 | ヨーロッパ初期中世(8) |
| 8 | 12世紀(9) |
| 9 | 13世紀(10) |
| 10 | 14世紀(11) |
| 11 | 15世紀前半(12) |
| 12 | 15世紀後半のイタリア(13) |
| 13 | 15世紀後半のアルプス以北(14) |
| 14 | 16世紀初頭のフィレンツェとローマ(15) |
| 15 | まとめ |
| 16 | 16世紀のヴェネツィアと北イタリア(16) |
| 17 | 16世紀初頭のアルプス以北(17) |
| 18 | 16世紀における「美術の危機」(18) |
| 19 | 17世紀前半のカトリック世界(19) |
| 20 | 17世紀のオランダ(20) |
| 21 | 17世紀後半から18世紀にかけてのイタリアとフランス(21、22) |
| 22 | 18世紀のイギリスとフランス(23) |
| 23 | 18世紀末から19世紀初頭のヨーロッパとアメリカ(24) |
| 24 | 19世紀のイギリスとフランス(25) |
| 25 | 19世紀末(26) |
| 26 | 20世紀前半(27) |
| 27 | 20世紀前半(27)続き |
| 28 | 20世紀後半(28) |
| 29 | 書き換えられる美術史(28) |
| 30 | まとめ |
|
・章が変わるごとに「予習プリント」を提出してもらいます(期日の授業開始時に提出。それ以降は受け取らないので注意すること)。 ・授業の終わりに簡単な「おさらいクイズ」を出します。解答を出席カードの裏に書いて提出しないと、その日は「出席」と見なしません。 ※出席の取り方、提出物に関するルールを第1回目の授業で説明します。 |