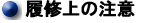| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 福井 憲彦 教授 | 4 | 2~4 | 通年 | 木 | 4 |


| 1 | どのくらいの受講生がいるかで進め方や用意すべきコピー数も違ってくるので、受講する学生は必ず出席してください。第1回目はアイスブレイキングのための顔合わせの集まりとし、私からは授業の進め方について説明します。履修する学生諸君の志向を知るために、受講生の自己紹介や履修外国語の種別、希望についても簡単に述べてもらうつもりです。 |
| 2 | 外国語による歴史関連文献の多様な種別について、主として英語文献を中心に専門研究書、一般書、研究論集、専門雑誌、雑誌論文、図録、各種史資料、新聞、定期刊行物など、実物やコピー事例をもとに解説します。私からの基本的説明に加えて、たとえば単行本や雑誌等の表紙や表紙裏の記述から、どのような情報が読み取れるのか、履修の学生諸君と対話しながら進めます。次回、または次次回から開始する輪読用のテキスト(コピー)を配布予定。 |
| 3 | 第2回目の続き、または輪読開始(受講生数と進捗状況によって判断)。 |
| 4 | 第1テキスト輪読開始。 (第1テキストは Atlas of diasporas から扉表裏・謝辞・目次・序章を選択する予定) |
| 5 | 第1テキスト輪読継続。 |
| 6 | 同上。 |
| 7 | 同上。(第2テキストとして同書Armenian Diaspora を予定、コピー配布) |
| 8 | 同上。中間の小テスト(ただし第1テキストの進捗度によっては実施の回が前後することがあります。) |
| 9 | 第2テキスト輪読開始。 |
| 10 | 第2テキスト輪読継続。 |
| 11 | 同上。 |
| 12 | 〃 |
| 13 | 〃 |
| 14 | 第1学期使用テキストの内容について議論。(第3テキストとしてThe Origins of the Modern World の一部分を予定。9月以降に備えてコピーを配布) |
| 15 | 第1学期について理解力確認の総括。 |
| 16 | 第2学期開始に当たっての留意点確認と第3テキスト輪読開始。 |
| 17 | 第3テキスト輪読継続。 |
| 18 | 同上。 |
| 19 | 〃 |
| 20 | 同上。(第4テキストとして雑誌論文を予定。コピーを配布) |
| 21 | 同上。 |
| 22 | 同上。中間の小テスト(ただし第3テキストの進捗度によっては実施の回が前後することがあります。) |
| 23 | 第4テキスト輪読開始。 |
| 24 | 第4テキスト輪読継続。 |
| 25 | 同上。 |
| 26 | 〃 |
| 27 | 〃 |
| 28 | 〃 |
| 29 | 〃 |
| 30 | 第2学期について理解力確認の総括。 |
| 受講者の英語読解力の状況をみて進度は調整します。それに応じてテキストごとの時間配分が変わる可能性もあります。速読というより、何よりまず英語の歴史文献に馴れること、しっかり理解して読み進める力をつけることを重視するからです。授業の進度はそれほど上がらないことが予想されます。能力が高く先へ進みたい受講者には、授業にプラスして別途テキストを用意することも可能ですので、相談のうえ考えましょう。 |