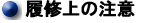| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 渡辺 学 教授 | 2 | 3~4 | 第2学期 | 火 | 2 |


| 1 | コミュニケーションの基礎(導入) |
| 2 | 会話の公理、ルール |
| 3 | 雄弁と沈黙、コンテクストへの依存度 |
| 4 | バーバル・コミュニケーション、ノンバーバル・コミュニケーション |
| 5 | 〃 |
| 6 | コミュニケーション・ジャンル、コミュニケーション・スタイル、視点 |
| 7 | コミュニケーション・ストラテジー |
| 8 | デジタルニューメディアにおけるコミュニケーション・ストラテジー |
| 9 | 会話分析、談話分析 |
| 10 | インタラクションの言語学 |
| 11 | 異文化の理解へ向けて |
| 12 | パフォーマンスとしてのコミュニケーション |
| 13 | 新しいコミュニケーションの可能性 |
| 14 | 授業のまとめ |
| 15 | 自主研究 |