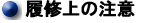| 1 |
教育心理学概観:定義、課題、研究法、行動主義と認知主義、カリキュラム、教育目標など |
| 2 |
発達の諸相:発達課題、人格の発達、生涯発達、発達の障害など |
| 3 |
認知発達:ピアジェの理論、言語、記憶、思考などの発達、知識獲得など |
| 4 |
青年・成人・高齢者:アイデンティティ、自己実現、生涯教育、生涯学習など |
| 5 |
学習の障害と指導:幼児・児童・生徒の学習障害とその指導など |
| 6 |
発達の障害と精神障害:発達障害の諸相と、さまざまな精神障害など |
| 7 |
学習のメカニズム:理論、教科の学習、学習の転移、学習の動機づけなど |
| 8 |
授業と学習指導:メディアやコンピュータを利用した学習指導など |
| 9 |
教師の役割と心理:あるべき教師像を求めて(教師の立場から、子ども・保護者の立場から) |
| 10 |
学級集団:交友関係や教師-生徒関係、子どもと学校を取り巻く環境の変化 |
| 11 |
いじめと攻撃性:いじめと不登校、いじめの種類、いじめと適応、いじめと障害児者 |
| 12 |
体験活動による学びと社会性の発達:体験活動の意義、種類、事例など |
| 13 |
知能・才能:才能や測定の問題、早期教育など、創造性、認知スタイルなど |
| 14 |
学力:学力不振、学力観、(個性、個人差)など |
| 15 |
測定・評価:考え方、方法、テスト作成、進路指導など・まとめ |