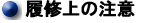| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 宮盛 邦友 准教授 | 2 | 2~4 | 第2学期 | 木 | 4 |


| 1 | 啓く |
| 2 | 自己理解・子ども理解とアイデンティティ・関係性 |
| 3 | 子ども問題としての登校拒否・不登校、少年非行、児童虐待 |
| 4 | 『生徒指導提要』と子ども・若者支援実践・政策 |
| 5 | 人間発達援助者としての教師と人間発達援助実践としての教育実践 |
| 6 | 人間形成における〈援助〉をめぐる問題 |
| 7 | 〈援助〉と〈教育〉との関係について:〈おとなが子どもを援助すること〉は〈おとなが子どもを教育すること〉とどう違うのか |
| 8 | 〈援助されること〉と〈自立性〉との関係について①:過保護の問題性 |
| 9 | 〈援助されること〉と〈自立性〉との関係について②:「善意と偽善」の問題 |
| 10 | 〈援助されること〉と〈自立性〉との関係について③:反精神医学・反教育学が問いかける問題性 |
| 11 | 〈援助されること〉と〈自立性〉との関係について④:「発展途上国への開発援助」おいて誰にとって何が援助となるのか |
| 12 | ジョイント・レクチャー |
| 13 | まとめ |
| 14 | ふりかえり |
| 15 | 結ぶ |