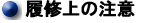| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 山本 芳明 教授 | 4 | D/M | 通年 | 月 | 4 |


| 1 | ガイダンス |
| 2 | 『門』を読む(1) 第一章~五章 |
| 3 | 同上 (2) 第六章~十章 |
| 4 | 同上 (3) 第十一章~十五章 |
| 5 | 同上 (4) 第十六章~二十一章 |
| 6 | 同上 (5) 第二十二章~二十三章 |
| 7 | 同上 作品全体に関する討議 |
| 8 | 『漱石研究』第17号前半をよむ(1) |
| 9 | 同上 後半をよむ(2) |
| 10 | 『真珠夫人』をよむ(1) 「奇禍」~「ユージット」 |
| 11 | 同上 (2) 「美奈子」~「汝妖婦よ」 |
| 12 | 同上 (3) 「面罵」~「破裂点」 |
| 13 | 同上 (4) 作品全体の討議 |
| 14 | 研究史の総括 |
| 15 | まとめ |
| 16 | 第2学期のガイダンス |
| 17 | 履修者による発表(1) |
| 18 | 前回の発表に対する質疑・応答 |
| 19 | 履修者による発表(2) |
| 20 | 前回の発表に対する質疑・応答 |
| 21 | 履修者による発表(3) |
| 22 | 前回の発表に対する質疑・応答 |
| 23 | 履修者による発表(4) |
| 24 | 前回の発表に対する質疑・応答 |
| 25 | 履修者による発表(5) |
| 26 | 前回の発表に対する質疑・応答 |
| 27 | 履修者による発表(6) |
| 28 | 前回の発表に対する質疑・応答 |
| 29 | 授業のまとめ |
| 30 | 予備日 |
| 授業の計画は流動的で、履修者の希望を考慮して、計画を変更することもあります。 |