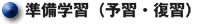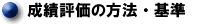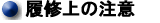| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 塚越 健司 講師 | 2 | 1~4 | 第2学期 | 月 | 3 |


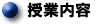
| 1 | ガイダンス(情報社会とは何か) |
| 2 | 情報社会の権力構造 |
| 3 | 再帰的近代化とは |
| 4 | 近代化とメディア |
| 5 | フェイクニュースとフィルターバブル。Post Truth(脱真実)とは何か? |
| 6 | 仮想現実(VR)とメディア |
| 7 | 拡張現実(AR)とメディア |
| 8 | 中間テスト |
| 9 | ハッカーの歴史とその活動1(カウンター・カルチャーと政治的ハッキング) |
| 10 | ハッカーの歴史とその活動2(ウィキリークスとハクティビズム) |
| 11 | 人工知能とその発展1(人工知能の歴史と最新技術) |
| 12 | 人工知能とその発展2(未来の人工知能と人間の関係) |
| 13 | 人間の理性と感情の関係について(行動経済学の視点から現在のメディア・リテラシーを捉える) |
| 14 | 理解度の確認 |
| 15 | 到達度確認 |