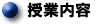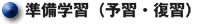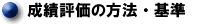| 1 |
イントロダクション―中世の武士・武士団とはなにか― |
| 2 |
移動する武士たち(1)都でつくられる人的ネットワーク |
| 3 |
移動する武士たち(2)婚姻と亡命・流刑 |
| 4 |
中世荘園の成立(1)新田氏の人的ネットワーク |
| 5 |
中世荘園の成立(2)新田荘の成立 |
| 6 |
治承・寿永の内乱(1)中世武士のネットワークと内乱 |
| 7 |
治承・寿永の内乱(2)中世武士のネットワークと地頭職 |
| 8 |
中世武士の奉公と所領経営(1)京・鎌倉の奉公 |
| 9 |
中世武士の奉公と所領経営(2)千葉氏・足利氏の散在所領経営 |
| 10 |
中世武士の奉公と所領経営(3)渋谷氏・三浦和田氏の散在所領経営 |
| 11 |
家督と惣領(1)惣領制とはなにか |
| 12 |
家督と惣領(2)家督と惣領の融合 |
| 13 |
「兄弟惣領」の出現 |
| 14 |
南北朝期の「兄弟惣領」 |
| 15 |
「家督制」の成立 |
| 16 |
第1学期の復習 |
| 17 |
地域権力としての武士団(1)武士団の軍事的テリトリー |
| 18 |
地域権力としての武士団(2)地域の町場に集う武士たち |
| 19 |
地域権力としての武士団(3)仏教を興隆する武士団 |
| 20 |
地域権力としての武士団(4)人返法の誕生 |
| 21 |
南北朝内乱と武士団(1)武士の一揆 |
| 22 |
南北朝内乱と武士団(2)本領の選択と領域権力化 |
| 23 |
中世武士団のイエ支配権(1)イエ支配権とはなにか |
| 24 |
中世武士団のイエ支配権(2)一門評定と幕府裁判1 |
| 25 |
中世武士団のイエ支配権(3)一門評定と幕府裁判2 |
| 26 |
惣領職の成立(1)「職」と惣領職について |
| 27 |
惣領職の成立(2)偽文書に記された「惣領職」 |
| 28 |
惣領職の成立(3)「職」の変質の歴史的背景 |
| 29 |
一年の総括 |
| 30 |
予備日 |