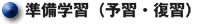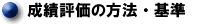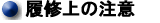| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 家永 遵嗣 教授 | 2 | 1 | 通年 | 火 | 3 |


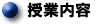
| 1 | テキスト『蒙古襲来絵詞』詞書を配布・確認し、発表当番を決めます。 |
| 2 | 『蒙古襲来絵詞』の絵巻部分を複製本によって観察し、モンゴル軍沈没船に関する水中考古学の成果など、関連する事項について説明します。 |
| 3 | 『蒙古襲来絵詞』の真贋に関する論争や、季長の本拠地に関する研究成果、季長が訪れた当時の鎌倉の姿など、関連する事象について説明します。 |
| 4 | 『蒙古襲来絵詞』の冒頭部分は破損が著しいため、教員が担当して、失われたとおぼしい記述内容の推定を示すとともに、担当者が行うべき訳文の提示要領を示します。 |
| 5 | 発表当番に従って、『蒙古襲来絵詞』の詞書を読み解いてゆきます。 |
| 6 | 『菅浦文書』628号「菅浦惣庄合戦注記」と『菅浦文書』323号「菅浦・大浦両庄騒動記」を配布し、釈読の発表当番を決めます。 |
| 7 | 近江国菅浦という惣村について、現状のスライドをまじえつつ、地理的・歴史的な環境・特徴を説明します。 |
| 8 | 発表当番の順序に従って、「菅浦惣庄合戦注記」・「菅浦・大浦両庄騒動記」を読み解いてゆきます。 |
| 当番を決めて史料を読み討論する「講読」の要領と、論文を読み解く要領の基本を体験します。『蒙古襲来絵詞』は和文脈を基本とする史料で、菅浦の史料は漢文の記述法が強く混じった漢字仮名まじり和文です。古文・漢文の知識を史料読解に応用する訓練となります。関連する学術論文を読んで、要約する訓練を行います。レポートを書く基礎になるトレーニングです。 |