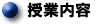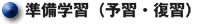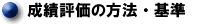●
日本文学講義Ⅱ
033-A-107
| 担 当 者 |
単 位 数 |
配当年次 |
学 期 |
曜 日 |
時 限 |
|
金田 房子 講師
|
4 |
2~4 |
通年 |
木 |
4 |

-
二つの俳諧紀行文を読みます。作者は男性と女性。前期は、有名な松尾芭蕉の初期の紀行文『野ざらし紀行』です。作品に現れている芭蕉の精神的な転機と思想のあり方にも注目してゆきます。後期は、九州の名主の妻から波乱の人生をおくった女流俳人諸九尼の『秋かぜの記』を取り上げます。行程が『おくのほそ道』と重なるところでは、両者を比較して読んでゆきます。それぞれ芭蕉自筆のテキストと版本をコピーしてテキストとして変体仮名にも親しみつつ、発句と文章とが織りなされて綴られる作品を鑑賞します。

-
季語・歌枕など俳諧作品の読解の基礎を理解するとともに、文学作品としての深みを分析する力を養う。女流俳人を通して近世の人の生き方を知る。あわせてくずし字解読の力も身につける。
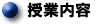
-
| 1 |
俳諧とは何か。 |
| 2 |
芭蕉の略歴①- 40歳頃まで- |
| 3 |
芭蕉の略歴②-41歳頃から晩年- |
| 4 |
『野ざらし紀行』-旅立ち-(プリント1) |
| 5 |
『野ざらし紀行』-小夜の中山-(プリント2) |
| 6 |
『野ざらし紀行』-大和行脚-(プリント3) |
| 7 |
『野ざらし紀行』-故郷~二上山-(プリント4) |
| 8 |
『野ざらし紀行』-吉野-(プリント5) |
| 9 |
『野ざらし紀行』-二人の敗者-(プリント6) |
| 10 |
『野ざらし紀行』-名古屋-(プリント7) |
| 11 |
『野ざらし紀行』-二月堂~大津-(プリント8) |
| 12 |
『野ざらし紀行』-旅の終わり-(プリント9) |
| 13 |
作品の構成 |
| 14 |
授業のまとめ |
| 15 |
予備日 |
| 16 |
近世の女流俳人 |
| 17 |
諸九尼の略歴① |
| 18 |
諸九尼の略歴②-発句作品を中心に- |
| 19 |
『秋かぜの記』-旅立ち-(プリント1) |
| 20 |
『秋かぜの記』-不破~熱田-(プリント2) |
| 21 |
『秋かぜの記』-三河路-(プリント3) |
| 22 |
『秋かぜの記』-大井川~蔦の細道-(プリント4) |
| 23 |
中略部分の解説 |
| 24 |
『秋かぜの記』-奥州路へ-(プリント5) |
| 25 |
『秋かぜの記』-浅香山・信夫の里-(プリント6) |
| 26 |
『おくのほそ道』-浅香山・信夫の里- |
| 27 |
『秋かぜの記』-笠島-(プリント7) |
| 28 |
『おくのほそ道』-笠島- |
| 29 |
授業のまとめ |
| 30 |
予備日 |

-
講義形式
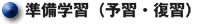
-
テキストを読み、自分の言葉での現代語訳を考える(約30分)
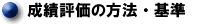
- レポート:60%(前期30%・後期30%)
- 小テスト:20%
- 平常点(クラス参加、グループ作業の成果等):20%
- レポート等は、コメントを付与の上返却する。

-
授業内で紹介する。