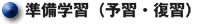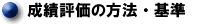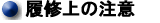| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 菅野 賢治 講師 | 4 | 2~4 | 通年 | 金 | 2 |


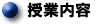
| 1 | イントロダクション 漢語文化圏という考え方 李用熙のいう「ひまわり現象」について考える |
| 2 | 前史 キリスト教西洋と東アジア |
| 3 | 日本 17世紀初め:フランソワ・カロンが見た江戸時代の日本 |
| 4 | テクスト購読(フランソワ・カロンが宰相コルベールに宛てた意見書) |
| 5 | ヴィエトナム 17世紀:アレクサンドル・ド・ロードの業績 |
| 6 | テクスト購読(ド・ロードの回想録) |
| 7 | 中国 17~18世紀:典礼論争とは何か(1) |
| 8 | テクスト購読(ル・コント神父の書簡) |
| 9 | 中国 17~18世紀:典礼論争とは何か(2) |
| 10 | 黄嘉略の生涯、ならびに18世紀フランスの中国観 |
| 11 | 朝鮮 18世紀:ラ・ペルーズが「見た」朝鮮 |
| 12 | テクスト購読(ラ・ペルーズの旅行記より) |
| 13 | 琉球 1840年代:フォルカードの琉球滞在 |
| 14 | テクスト購読(フォルカードの滞在記) |
| 15 | 自主研究 |
| 16 | 筆記 遠藤周作『女の一生 一部 キクの場合』(新潮文庫) ジュール・ヴェルヌ『必死の逃亡者』(創元SF文庫) ピエール・ロチ『お菊さん』(岩波文庫) いずれかをあらかじめ読んでおき、「東西文化の出会いと確執」という観点から考えたことを記す |
| 17 | ヴィエトナム 1858-1867年:チュオン・ヴィン・キーとフランス領インドシナの成立 |
| 18 | テクスト購読(チュオン・ヴィン・キーの書簡) |
| 19 | 日本 1860~70年代:長崎の隠れ切支丹――プティジャン神父とド・ロ神父 |
| 20 | テクスト購読(プティジャン神父の手紙) |
| 21 | 中国 19世紀末:ジュール・ヴェルヌの作品の中の東アジア |
| 22 | テクスト購読(ヴェルヌ『必死の逃亡者』) |
| 23 | 日本・中国 1876年:エミール・ギメの中国、日本旅行 |
| 24 | テクスト購読(ギメ『東京日光散策』) |
| 25 | 日本 1870年代:横浜のフランス語新聞『レコー・デュ・ジャポン』 |
| 26 | 朝鮮・日本 1880年:リデル神父による『朝仏辞典』 |
| 27 | テクスト購読(リデル神父の書簡) |
| 28 | 日本 1887/1894年:お菊さんの言い分――ピエール・ロティ対フェリックス・レガメー |
| 29 | テクスト購読(ロティ『お菊さん』ならびにレガメー『お菊さんの桃色手帖』) |
| 30 | 理解度の確認 |