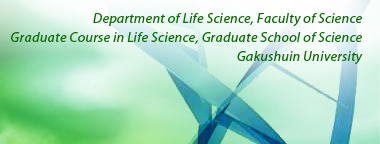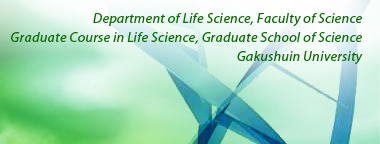| 有機合成反応をベースに「ガン治療を目的」とした開発研究 |
 |
| 有機化学は、我々の身の回りのどんなところに関わっているだろう?食品、医療、医薬、家電製品などへの幅広い応用を思い浮かべる人も多いだろう。有機合成反応の新規開拓をベースに、ガン治療を目的とした非天然型酵素阻害剤の開発研究を手がけている。 |
 |
 |
 |
| 【教員】 化学科 |
| 教授:中村浩之、助教:潘鉉承 |
 |
|
|
| レーザー顕微鏡を用いて、「小さな分子機械」の謎を解明 |
 |
| 細胞内のミトコンドリアにあるATP合成酵素は、軸をくるくると回す地球上でもっとも小さいモーターである。その大きさはわずか10万分の1ミリ。たったひとつの分子がモーターとして働く。発明したレーザー顕微鏡を用いて、このような小さな分子機械の謎を解明しようとしている。 |
 |
 |
 |
| 【教員】 物理学科 |
| 教授:西坂崇之、助教:政池知子 |
 |
|
|