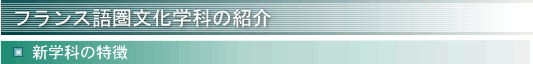1.コース制
| 1)新学科の大きな特徴はコース制です。フランス語圏文化学科では、以下の4つのコースを設定します。
*広域コースの「広域」とは?
2)コース選択の流れ
1. 分野の広域性(言語、文学・思想、舞台・映像以外の幅広い分野をカバーする) イメージ(漫画、アニメ、イラストレーションなど)、音楽、モード、食、都市などについての研究。 2. 地域の広域性、多様性 フランスのみならず、カナダ、アフリカ、カリブ海周辺などに広がるフランス語圏文化の地域研究。 *各コース別の科目:「フランス語圏文化入門」(1−2年次)「フランス語圏文化講義」(2−4年次)「フランス語圏文化演習」(3−4年次)の3種の科目群。
◎学生が自分の関心を徐々に絞っていくことができるようにしてあります。 ◎コースごとの履修要件を「フランス語圏文化講義」「フランス語圏文化演習」それぞれ1つと、ゆるやかなものにしています:このことによって、学生は多様な領域に触れながら、その中で自主的に自分の関心を位置づけることができます。 |
2.3年ゼミナール、4年ゼミナール
| 3年ゼミナール、4年ゼミナールは必修で、学生は自分のコースの指定するゼミからひとつを選択します。少人数の演習形式によって、ゼミ担当教員の選んだテーマを深く研究します。 |
3.卒業論文・卒業翻訳・卒業演習
4年次には大学での研究の総仕上げとして、「卒業論文」「卒業翻訳」「卒業演習」からひとつを選び、履修します。 1)「卒業論文」 2)「卒業翻訳」( 2007 年度から導入されました) 3)「卒業演習」 |
4.フランス語教育のさらなる充実
| 従来よりフランス文学科の語学教育はかなり密度の高いものでしたが、新学科では、さらに語学教育を充実させます。 1)1、2年次のフランス語 1年次、2年次ではおのおのフランス語の学習は、必修として週5回(1回90分)あります。その中心となるのが「基礎演習I」(1年次の専門科目)と「基礎演習II」(2年次の専門科目)です。「基礎演習I」では、フランス語の仕組み、基礎的な文法知識、また基本的な語彙、表現を正確に覚えたうえで、簡単なテクストが読めるようにします。また「基礎演習II」では、中級文法を学びながら、より高度なテクストの読解ができるようにします。 またテクストを読むだけでなく、話す・聞くという実践的なフランス語力を養うために、ネイティヴ教員の授業も多く置かれています。1年次には週1回、2年次には週2回ネイティヴ教員によるフランス語の授業が必修です。さらに3年次以上の専門科目の授業においても「フランス語演習」(必修)のほか、ネイティヴ教員による授業を選択することができます。 2)3年次以上のフランス語 |
5.きめ細かい論文指導
| コース制によって学生の関心を明確化すると同時に、卒業論文、卒業翻訳を選択する学生向けに「論文指導」(おもに3年次)の授業を設け、どのように論文を書くべきかの実践的な訓練を行います。 また「卒業論文」「卒業翻訳」を選択する予定の3年次の学生には「卒論準備プログラム」を用意し、卒論の準備を支援します。具体的には、基本的な文献を読んでレポートを書き、教員の指導を受けることによって、自分の関心がどこにあるのかを見つけられるようにします。 |
6.資格試験
| 平成20年度より、2年次以降の学生にはフランス語実用検定に代わってTCF(フランス語実力試験:フランス教育省が全世界100ヶ国以上で行っているフランス語の学力検定試験で、英語におけるTOEFLのようなもの)の受験を推奨しています。演習科目「フランス語実習」の受講者は必ずこの試験を年に一回(12月の予定)受験することになります。試験は筆記試験のみ(聴き取りあり)、90分です。試験の詳細などについては、上記演習科目の授業内で説明します。 |
7.海外への留学、研修
| 学習院大学では、リヨン第2大学、パリ第10大学、パリ第7大学と協定を結び、学生・大学院生の留学を支援しています。この制度を利用すると、受け入れ大学での授業料免除が受けられるほか、単位互換、宿舎の確保などがスムーズに行われます。(協定留学には選抜試験があります) また協定留学だけでなく、一般の留学についても、学習院大学内部で「安倍奨学金」を受けることができます。(「安倍奨学金」の応募者には選抜の審査があります) |