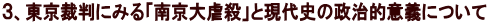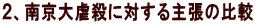





【東京裁判に見る「南京大虐殺」】
私は、「南京大虐殺」を通して現代史の政治的意義について問うというこのテーマの中で、この事件が実際にあったのか、あったとすればどの位の規模であったのか、それは何を根拠として述べられているものなのか、そしてそれが今日の政治にどのような影響を与えているのかについて考えていく中で、東京裁判からこの問題について考えてみました。
東京裁判の裁判記録の上でこの事件は、起訴状の訴因第45に「南京暴虐事件」という項目で載せられています。そこには、目撃者の証言によるとされる南京において日本兵が行ったとされる残虐行為“多くの兵士は酔っていた。中国人の男女子供を無差別に殺しながら歩き回り、遂には大通りや裏通りに被害者の死体が散乱したほどであった。”や“多くの婦女は、強姦された後に殺され、その死体は切断された”について具体的数字を挙げながら述べられています。ここで述べられている内容は、家永氏による教科書裁判で「南京大虐殺」が注目を集めることとなった辺りから、日本人が一般的な認識として抱くようになったと思われる「南京大虐殺」に対するイメージ、つまり残虐行為(殺人、強盗、掠奪、強姦)の数々について生々しく語られています。
訴因として上記のように述べられたものの、実際はこの事件に対する判決は成されませんでした。それは、裁判記録には訴因第45は述べ方があいまいであるという理由によるもので、『日本軍がそれらの場所を攻撃し、住民殺害を不法に命じ、行わせ、許可し、それにより一般人、武装解除された軍人を不法に殺害したとされるこの訴因からは、不法な殺害という主張の基礎が、攻撃の不法性に対して置かれるのか、戦争法規の違反に置かれるのか、その両方に置かれるのかが明瞭ではなく、もし、前者に置かれる場合は、その戦争が不法でなかったと認定された場合、殺人という起訴事実は不法な戦争の遂行という起訴事実と共に成立しなくなり、後者に置かれる場合は、訴因第54と第55の起訴事実と重複していることとなる。このような事情のもとにおいて殺人の起訴事実の妥当性に関して、どのような意見も表明する必要がないと認めて、われわれは、判決を与える必要がないと決定した。』と述べられています。
事件自体には、判決が成されなかったわけですが、南京において残虐行為を行ったとされる軍隊の指導者に対する追及はなされました。第10軍を含む中支那方面軍事司令官に任命され、軍隊を率いて、1937年12月13日に南京城を攻略した松井石根氏は、有罪とされています。理由としては、『残虐行為が広く行われたことは日本人証人によって、否定されたが、色々な国籍の、また疑いのない信憑性のある中立的証人の反対証言は圧倒的に有力である。(中略)これらの恐ろしい出来事が最高潮にあったとき、松井氏は同市に滞在していた。自分自身の観察と幕僚の報告によって、彼はどのようなことが起こっていたかを知っていたはずである。憲兵隊と領事館から自分の軍隊の非行がある程度あったと聞いた事をかれは認めている。』などが挙げられ、裁判所は松井氏が自らの率いる軍隊が行った事を知っていた証拠は十分ある上に、軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限を持っており、この義務の履行を怠ったことについて、犯罪的な責任があると認められるというものです。
次に、世界の国際法学会で、東京裁判について研究し、考える上で極めて貴重な文献であるとして高く評価されているパル判事の意見書から、「南京大虐殺」に関する見解についていくつかポイントとなることに触れていきたいと思います。『「南京暴虐事件」を立証するために、たくさんの証拠が提出されたが、証拠の数の多さだけで、起訴事実が絶対に真実であると保証する事はできない。それは、あることがおこるのを見たという人の言い分が必ず信じられるとは限らないと誰もが承知していることからもいえることである。また、「戦争犯罪」というもの自身が、復讐を生み出すもとであり、戦闘中の事件であるので、感情を挟まず考えなくてはいけないが、目撃者が昂奮していたり、偏見の目を持った観察者であったりという困難がある。また、戦時宣伝の存在を忘れてはいけない。過去の戦時宣伝による経験が、被告の考え方に影響を及ぼし、敵側から出た虐待の事件に関する戦時宣伝を、是認するか拒絶するかのどちらかの方向に向けさせることが出来るか否かという適当な考慮を必要としている。このような理由から、南京暴虐事件に関して発表された記事について、世界は誇張されているものであるという疑念を持たないでは受け取り得ないということである。チャールズ・アディス卿がこの事件に対して述べた事は、「戦争を交えている二国間において、戦闘員が宣伝に訴えることによって、世論を自己に優位に仕向けさせようという危険性が存在している。偏見や感情の激昂により、戦いの真の係争点を曖昧にしてしまう目的のために拡大され、曲解されるのである。」以上のような目的が、この場合においても避けられないのである。証拠に対して悪く言う事の出来る事柄をすべて考慮に入れても、南京における日本兵の行動は凶暴であり、深刻であったことは疑いない。弁護側は、南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった。彼らは、単に<U>誇張されていることを訴えているのであり、かつ退却中の中国兵が、相当数残虐を犯したことを暗示したのである。』
【感想】
東京裁判において、判決のなされなかった「南京暴虐事件」ですが、松井氏が有罪とされたことや、パル判事の見解から私は、この事件は実際にあったのだろうと考えるに至りました。しかし、規模の点ではこれもパル判事が述べられているように、戦時中の証言である故に、偏見を持った感情から証言されることもあるだろうし、また戦時宣伝の影響も考えられるために、全面的に証言された話を信じる訳にはいかないとも考えます。現代史は証拠が少なく、自国の利益のために拡大され、曲解されるということが、これらのことから良く分かりました。「神の視点」を持つ人が存在しない限り歴史の真実を知る事はできない、私たちは何らかの偏見がかかったフィルターを通すことによってしか歴史を知ることができないのです。このような意味において、これからも曖昧な現代史は、政治的な道具として使われていくことでしょう。私たちは、より曇りのない眼でそれを見守っていくために、偏りのない情報収集により、他人の情報に惑わされる事なく自分の考えの核を持って世界の流れを見守っていく必要があるのだと思いました。