世界の果てからメッセージ
随筆 「荒野に立ちて」
眞嶋 史叙
ごつごつと赤茶けた岩山の狭間から、あの果てしない戦乱の地アフガニスタンを望んだカイバル峠。潅木が点在するだけの荒涼とした大地が、踏み込んではならない地の果てを魅せつけていた。なぜ夫は私をそこに誘ったのだろうか。

宗教者ではない私は、生涯カンダタのように虫けら同然の生き方をするかもしれない。そんな私でも、何かを得たいと思ってのことか、その後八年間異文化の海外で研究生活をつづけてきた。その間、さまざまな人々と知り合い、助けられ、彼らの生き方、そして世界観に惹かれてきた。
異文化に飛び込むといっても、ただ空間的に移動し、これまで培ってきた狭雑な日常や慣習を持ち込んだのではだめだ。英国留学中そう気付かされたのは、樫の羽目板に囲まれて薄暗い、と或るカレッジのダイニングルームでのことだった。当カレッジのゲストとしてその夜を過ごした私は誰よりも早くその四百年の歴史を誇る食堂で朝食を貪っていた。そこへ偶然現れたオランダ人招聘教授。日本人の私も読んだことのない日本文学の主人公の心理について滔々と語りだしたのだ。その時、はっと目の覚める思いをした。これ程大胆な異文化への跳躍を自分にはできるのかと。
冷静に考えれば、これはそれほど際立って強烈な事件ではなかった。ただ偶然に日本文学好きのオランダ人に出会ったというまでの話だ。凡庸な事件の印象が増幅したのはなぜか。第一には、この教授が数学者であったこと。恥ずかしながら、学問的な先入観が私の中にあるのだろう。第二には、その場の雰囲気だ。その前夜、その食堂では正餐後の葡萄酒が饗された。平均年齢五十五歳のカレッジとあって、作法の厳しさはオクスフォード随一。秘蔵のクラレットが時計回りに大食卓を巡り、黒いガウンに身を包んだドン達が談義にふけっていた。左右正面と順に話を交しつつ。
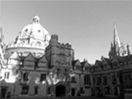
成程ドン達は華麗なる社交性と博識を備えている。しかし、地球を半周した最果ての地への関心は薄い。「島国どうし」という親近感は彼らにとって無縁の物だった。もちろん、バブル期以降日本へ招かれた教授も少なくないのだが、或人によれば在日中の孤独を紛らわせたのはドストエフスキーだったとか。よって、この無関心が第三の要因だ。その朝私はおなじみの無名性を心地よく感じながら、濃厚なマーマレードを味わっていた。だから、日本人少年の心理を嬉々として語る姿に不意をつかれたのだ。彼も本当は前夜の紳士クラブ的文化に疎外感を感じていたのかもしれない。
異文化へ跳躍をするというのは難しいことだ。最近よく耳にする「越境transgression」とは、空間的な移動ではなくて文化や慣習の境界を越えていくことを指し、もともとは宗教的破戒を意味していた。多文化主義の現代社会にあっては、むしろ求められる資質の一つとなりつつある。そう考えると、現代人の原型は、無人島にて合理的な生活様式を固持したロビンソン=クルーソーにみられたのではなく、むしろ小人の国から馬の国へと自由自在に越境したガリヴァーにあったのではなかろうかと思われてくる。この人間風刺の傑作を幼少から幾度となく父に勧められた。
ガリヴァーも最初はむしろ受動的に小人の国へ漂着している。越境する意思は馬の国で初めて芽生え、その後彼は家族を捨て人間界をあとにした。当初から明確な意志を持っていたのは『天路歴程』のあの男だ。福音の天使に導かれた男は耳に指をつっこんで叫ぶ、「命、命、永遠の命」と。そして引き留める家族や隣人を押し切り旅立った。新境地へ旅立つということは、自分と向き合って孤独を受け入れ、既存のしがらみを振り切ることから始まる。そこで初めてこれまでとは異なる新たな共感の喜びを味わうことができるのだ。その際家族や隣人はむしろ邪魔になるという。
一七世紀の英国はバニヤン、デフォー、スウィフトの文学のみならず、レンのバロック建築やニュートンの科学も生み出した。宗教的には旧教と新教の狭間で揺れ、大西洋を跨ぐ植民地の形成そしてグローバル化が進んだ。まさに英国にとって越境の時代であった。植民地との奴隷貿易で得た莫大な利益を元手に築かれた、オクスフォードの優美な街の影法師。象徴的な丸屋根はレンの技によるものだ。今はかたくなにその遺産を守ろうとしている。世界中から観光客や学生、研究者が集まる街。そこには、それぞれが何かを得ようと孤独になる時、そして分ち合う時があるのだ。
越境のスタイルには様々ある。夫の高校時代からのお気に入りは『ヘラルド=トリビューン紙』であった。新聞の端に書かれるベタ記事。地域紛争の状況を備に追えるから、良いのだという。彼はそこに福音の天使を見ていたのかもしれない。紛争地域での生活をカメラに収め、帰国途中機上で読むベタ記事を手にまた飛び立つ。そんな仕事に憬れていた。しかし、「最果ての地」は案外身近なところにあるのかも知れない。宗教、民族、ジェンダー、性的志向、所得格差。その境を越えて対岸に身を投げる。プチ越境したいなら『ビッグ=イッシュー誌』の駅前講読がお勧めだ。
カイバル峠を訪れてから彼此十年になる。この間彼の地は、9.11事件を契機に攻撃をうけ、タリバーン政権下の中世社会的な軛を打破しつつも戦闘が続く。「広い視野」に立つということは、まず己を見据え、異文化を「異」とせず、自己と世界の間を自由自在に行き来して、最果ての地に住む生身の人間に共感できるということではなかろうか。グローバル化が進む現代、物理的な世界の広さは縮まったのだが、私たちの心の中ではその準備ができているのか。多文化主義を想う時、私を彼の地へ導き、共感理論に基づく世界平和の倫理を追求し続けるわが夫を尊敬してやまない。
まじま しのぶ ☆ 学習院輔仁会雑誌 (2008年) No. 231 掲載
問題点のご指摘・お問い合わせなどございましたら眞嶋史叙までお知らせください。
Updated: 2023-05-07
